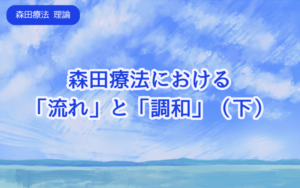森田療法における「流れ」と「調和」 (上)
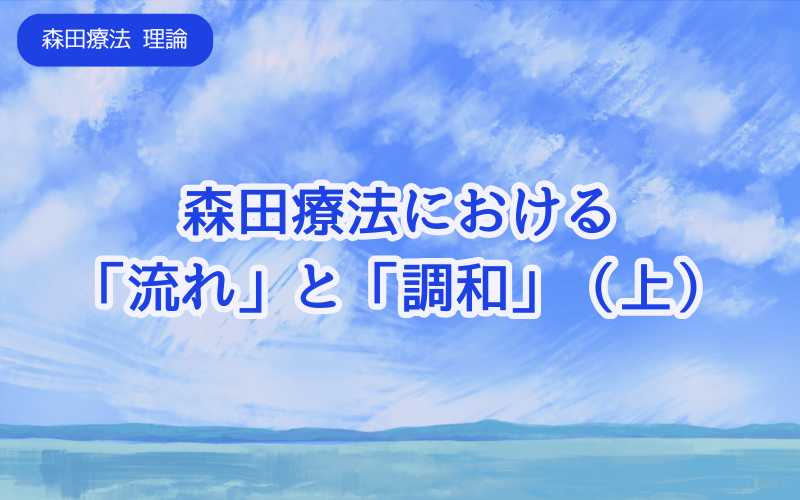
森田療法は人間の全体を扱う
森田療法は、曼荼羅にたとえられるかもしれない。
曼荼羅は様々な神仏を網羅し、悟りへの体験を視覚化して描かれたものだという。それはひとつの小宇宙になっている。
森田療法も一人の人間を、あたかも曼荼羅のように、小宇宙として扱う。
人間の悩みのみでなく、その全体を扱い、また人間を自然という全体の一部として扱う。
森田療法は、その人の症状だけを問題にするのではなく、身体、行動、感情、思考、価値観、欲望などを扱い、それぞれの相互作用を考える。
この治療法は「症状」という自分のほんの一部のことにとらわれて悩んでいる人を、その人の全体に戻していく治療法なのである。
人間の全体もまた自然の一部である。
本来であれば、人間は自然の一部として調和的に生命を維持し活動し、また周囲の環境とも調和をはかろうとして生きるはずである。
それが森田療法の前提である。周囲の環境と調和して生き、活動することは、人間の本来の姿なのである。
森田博士は生前、自身の治療法を森田療法とは呼ばず「自然療法」と言った。
彼の治療法は人間の心身を本来の自然な状態へと戻し、環境に調和させ、備え持っている能力を発揮させていく治療法である。
しかし、森田療法はまるで曼荼羅のように把握しにくい。悩む人は確かに症状を克服していくが、そのプロセスを図式化したり、一定の手順に表したり、回復者が治癒過程で体験したことを言語化することが非常に難しい。
そのむずかしさが、現在までに森田療法に対する様々な誤解を生み、また十全な理解を妨げる原因となっている。
森田療法は動きを扱う
森田療法理解が困難と言われる要因の一つは、森田療法が現実や人間の精神を見るときに、
それを「動き」として見ることにあるかもしれない。私たちは、「心」をひとつの実体、静的なものとする見方に慣れすぎているのだ。
内界と外界との間に、相関的に絶えず流動変化しているもの、これが精神というものである。薪でもない、酸素でもない。燃焼の現象が、そのまま精神である
(森田正馬 神経質の本態と療法)
森田博士は精神を固定した実体とは考えず、ひとつの現象であると考えていた。
人の外界と内界との相互作用について、森田博士はこんな褝の言葉をよく引用した。
鐘が鳴るかや撞木が鳴るか、鐘と撞木の間が鳴る
つまり鐘をつく撞木が外界の事象であり、それがあたって内界の鐘が振動する。これが精神現象というものであると言う。
そして彼は言う。
精神の研究は、必ず外界と自我との相対する間に求め、その変化流転のうちにきわめなければならない。
(森田正馬 神経質の本態と療法)
彼の精神療法は、「動き」に焦点を当てているのだ。たとえば、相互作用、変化、流れ、バランスそして平衡、調和などである。彼はこれらのもののなかにある「法則」を研究したのである。そして彼の治療とは、これらの「動き」に影響を与え、患者の生き方を自然な状態、調和的な状態にしていくものである。
心の「動き」に法則を見る
森田正馬は、無意識や下意識の存在を否定はしなかった。
しかし、彼の無意識の定義はフロイトのものとは違っていた。彼は、無意識すら人間の意識の自然な流れの一部と見ていた。
彼にとって重要だったのは、無意識も下意識も含む流れのなかで起こってくることだった。
「動き」それ自体に法則を見る森田の鍵概念としては、「精神交互作用」「感情の法則」などがある。
心を動きとして見たときに、そこにはバランスをとるという働きが考えられる。それを彼は「精神の拮抗作用」「欲望と不安の関係」などで表現した。ひとつの例として「精神の拮抗作用」を考えてみよう。恐怖という感情が起こる時、同時にそこには恐怖すまいという反対観念も起こる。恥ずかしいと感じると必ずその感情を隠したくなる。外出するとき鍵をかけると、本当に鍵をかけたのかという疑問が起こってくる。これは人間の心の自然な働きである。
拮抗作用が働かないとその人は衝動的になり、これが麻痺すると無謀な行動をとり、抑制作用が強すぎると、うつ的になる。拮抗作用が増進すると、強迫的となる。森田博士はそう言っている。(神経質の本態と療法)
このように彼の理論のなかには、精神の「動き」に基くものが多くある。そのため森田療法は、体験した者には明確だが、それを言葉で把握しようとすると明瞭でなくなる。自然な動きを完全に表現するのは不可能だからである。
森田療法の思想は禅仏教や老荘思想、ベルグソンなどに影響されていると言われている。
しかし療法の「動き」に焦点を合わせた考え方には武道の影響があると思う。森田博士自身が二つの武道に精通していた。彼は「居合」と「柔道」の有段者だった。
彼が武道の修行から学んだものは、動きの中にある緊張感、臨機に動く注意力、背水の陣、状況に即座に対応していくこと等ではないかと思う。もちろんこれらのものは、ただ影響を与えただけのもので、それが森田療法を作ったわけではない。
森田理論はただ心の「動き」だけを見るのではなく、神経質症を生む素地にある性格傾向を見ていた。彼等の心気症的性格、完全欲、理知性、自己中心性、自己内省性、強い欲望などについても理解をしている。彼はこれらの性格特徴を価値判断しなかった。彼にとってはこれらは人間の自然な特徴であり、価値判断の対象ではなかった。(つづく)