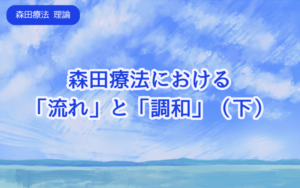理解と感じ(竹林公認心理師)

観念のやりくり
悩んだり、強迫観念にとらわれて苦しんでいる時などによくあることですが、私たちはどうも頭の中で結論を出そうとしてしまいがちです。
「なぜ自分はこんなに追い詰められて苦しいのだろう」と考えて、原因や対策を探し続けてしまう。
そのグルグル回りが始まると、どんなに頭の中で精神交互作用や思想の矛盾が理解できて納得できたとしても、「それなのになんで苦しみは消えないんだ!」と、さらに追い詰められてしまいます。
先日の森田正馬原著読書会で学んだことは、「論理的説得法で恐怖に打ち勝つとか、自信をつけるとかいう方法では、一時的に解決したとしても、再発を免れない」でした。
また、「理論から出発してそこに当てはめようとすれば、思想の矛盾となり、悪智となるが、純な心から出発すれば良智である」とも書かれていました。早い話が、私たちは観念でのやりくりでとらわれて苦しみに陥ってしまった訳ですから、そこからの脱出を観念のやりくりで行おうとすること自体が、どだい無理な話ということですよね。そうそう、この説明そのものが観念の世界での言い回しになりつつあります。
そうは言いながら、このあたりにとても深いヒントがあるような気がします。「論理的説得法では、決して再発を免れない」。
森田正馬がはっきりとこう言い切っていることは、とても大事なことですね。観念で追い詰められた世界は、観念では脱しきれない。
「理解」するということは、たとえば行動すればこうなりますよなどという、分かりやすい指導方法に現れてきます。
でもそれでは精神交互作用は断ち切れても、思想の矛盾は解消しない。
言い換えれば、できなかったことができるようにはなっても、深く抱えている辛さ、悶々とした気持ちの束縛からは自由になれないと言うことになります。
では、なぜ多くの方が目的本位と称して行動至上のアドバイスを行うのでしょうか。
答えは簡単、「分かりやすい」からです。
この分かりやすいというのは、相手にというよりも、むしろ自分がということです。自分が分かることしか相手には伝えられない。これこそが「理解」の世界から抜け出せていないということになります。
症状に出会ったときに、まずは症状のカラクリを「理解」して、次にとらわれから自由になる道も「理解」して抜け出そうとし、一見抜け出したかのようなつもりになって、人にも同じ「理解」の道を伝えていく。
この繰り返しが、森田療法が少しずつ違ったとらえ方になってきていると、私が感じる理由なのではないかと思います。
理解を手放す
これはなぜなのかと問うてみると、症状の成り立ちと同じように、私たち神経質者がもつ特性がそうしてしまったということです。
放っておくと、神経質者はすぐに頭を使って目に見える言葉や方法で、理解と解決の道を探してしまいます。
でもそれでは解決しないとしたら、どうしたら良いか。
それは頭を使わないこと、目に見える形で言葉を使わないこと、理解しないことだと思います。
ですから、理解したことを人に伝える必要はないのです。
一緒に体験したり生活したりしながら、感じる機会や環境を作ってみれば良い訳だし、もし一緒に生活できなくても、会って語り合いながら、日常生活のことを話したり聴いたりしていくこと、それで十分伝えられていくと思います。私たちはどんなに頭から離れようとしても、そんなに簡単に感性だけの人間にはなれませんから、思い切って論理と理解、言葉を捨てるくらいの気持ちでも大丈夫です。
目いっぱい意識して努力しても、この部分に関して言えば、とても無神経質の域に達することはありませんからご心配なく。
私たちは、この感じと頭のバランスがうまく取れずに偏ってしまっているだけですから、意識してこの偏りを反対側に傾けてみましょう。まっすぐだったら傾けると倒れますが、もともと偏っていますから、傾けても倒れることもなく、きっと「あっ、ちょうど良い感じだな」と気づくことでしょう。
私は、森田療法の神髄は頭の理解を越えたところにあるような気がしています。体系化もできないし、マニュアル化もできない。もしかしたらアカデミックな学問として伝えられるようなものではないのかも知れません。
それにしても、この様な森田療法が欧米などでも支持されているというのはすごいことだと思います。異なる言語圏では、森田の言葉にとらわれようがないからなのでしょうか。
みなさん、こんなことも思いながら、一緒に深く森田療法が伝える世界に触れてみましょう。
©竹林耕司「集まれ、勝手コラム」より